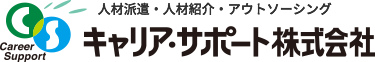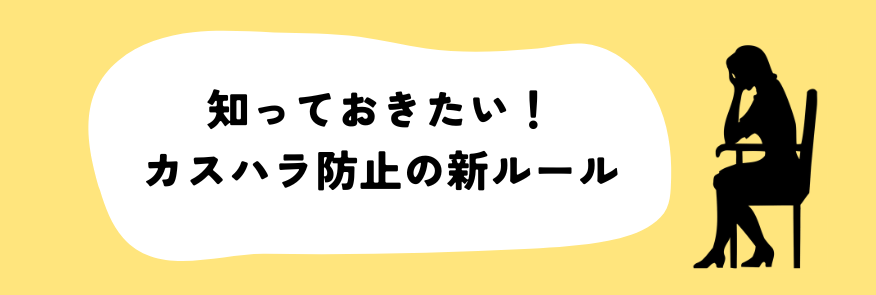
近年、深刻な社会問題となっている「カスタマーハラスメント(カスハラ)」について、最新の動向と対策の重要性をご紹介します。
今、なぜカスハラ対策が重要なのか?
カスタマーハラスメントとは、お客様からの理不尽な要求や暴言など、働く人の就業環境を著しく害する迷惑行為のことです。
労働者が安心して働ける環境を守るためにも、カスハラ問題への理解と対策は不可欠となっています。
2025年、カスハラ対策は新たな段階へ
2025年4月1日、全国で初めてとなるカスハラ防止条例が東京都、群馬県、北海道などで施行されました。
これらの条例では、「何人も、あらゆる場においてカスハラを行ってはならない」と明確に規定され、お客様だけでなく、企業や従業員に対してもカスハラ防止のための対応をとることが責務として定められました。
増加の背景と主なきっかけについて
カスハラが増加した背景には、SNSの普及によりお客様の発言力が大きくなったことが挙げられます。
企業側がお客様からの批判を恐れるあまり、理不尽な要求に応じざるを得ない状況も生まれています。
厚生労働省の調査(2024年、スーパー業界対象)によると、カスハラが発生する主なきっかけとしては、
・お客様からの無理な要求:68%
・お客様の勘違い:49%
・従業員の接客態度・言葉遣い:49%
などが報告されています。(複数回答)
カスハラが起こりやすい職種とは?
業種によってカスハラの発生状況には差が見られます。
カスハラ経験率が高い職種は以下の通りです。
・福祉系専門職員(介護士・ヘルパーなど):34.5%
・顧客サービス・サポート:30.7%
・受付・秘書:30.0%
・医療系専門職員(医師・看護師など):28.9%
厚生労働省は企業向けのカスハラ対策マニュアルを業種別に作成しており、2025年3月末には初めてスーパーマーケット業界向けのマニュアルが完成しました。
このマニュアルでは、具体的な対応方法として以下の例が示されています。
・不合理な問い合わせが繰り返される場合、管理職が対応を引き継ぎ、やめてもらうよう伝える
・威圧的な言動に対しては「怖いです」などと自分の気持ちを率直に伝える
・被害に遭ったときの対応手順を策定する
・従業員を対象にしたロールプレイング形式の研修を行う
その他、実際に行った企業の取組事例等も紹介されていますので、詳しくは厚生労働省のカスタマーハラスメント対策企業マニュアルをご確認ください。
まとめ
カスハラ問題は、もはや個々の企業だけの問題ではありません。
2025年4月には全国初のカスハラ防止条例が施行され、三重県桑名市では氏名公表という踏み込んだ対策も導入されています。
政府もカスハラ対策を企業に義務付ける法案を閣議決定するなど、法整備も進んでいます。
今後も、カスハラに対する社会全体の認識向上と、事業者・従業員・顧客がお互いを尊重し合える環境づくりが推進されることを願っています。